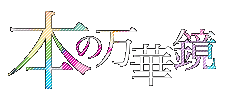- 本の万華鏡
- 第25回 あれもこれも和菓子
- 第1章 駆け足でたどる和菓子の歴史
- はじめに
- 第1章 駆け足でたどる和菓子の歴史
- コラム 和菓子デザイン5選
- 第2章 和菓子をめぐる風俗
- 第3章 文芸のお菓子箱
- おわりに・参考文献
第1章 駆け足でたどる和菓子の歴史
第1章では和菓子のルーツについて歴史をたどって紹介するとともに、和菓子文化が花開いた江戸時代の菓子商人の様子を取り上げます。
菓子と言えば果物であった時代
元来は「菓子」と言えば果物や木の実を意味しました。1603年刊行の『日葡辞書』【869.3-N728】でも”Quaxi(クワシ)”は「果実、特に食後の果物を言う」とあり、この時代になってもまだ菓子の意味は果物が中心であったようで、今も果物を「水菓子」と呼ぶのはその名残です。
このように長らく果物を意味した菓子ですが、一方で早くも奈良時代には現代に通ずる加工食品としての菓子の意味を併せ持つようになります。契機となったのは当時の海外文化の伝来で、古代史料に「唐菓子(からくだもの)」の名で現れる料理が唐(現在の中国)からもたらされました。これらは米粉等を主材料に甘味料等で味付け、油で揚げたものが多かったそうで、形や調理法は多種多様にあったようですが、現代にはわずかにお供え物として残るのみです。
和菓子の萌芽は平安時代に
やや時代は下って平安時代、『源氏物語』若菜【新別け-2】に「椿餅(つばいもちゐ)」という食べ物が登場します。物語中では蹴鞠を終えた殿上人達に供された椿餅ですが、室町時代の注釈書『河海抄』【本別3-26】では、餅の粉に甘葛あまずらという甘味料をかけ、椿の葉で包んだ餅菓子であると記されています。この椿餅もかつては唐菓子の一つでしたが、次第に日本文化に吸収され、日本人好みの「和菓子」となった早い例として知られています。
僧侶が運ぶ最新の海外文化
鎌倉時代以後、日本の菓子は飛躍的な展開を見せます。それを担ったのは僧侶です。宋(現在の中国)へ留学した彼らは、新たな教義とともに最新の食文化も持ち帰りました。「お茶と和菓子」と言えば、今や切っても切れない関係ですが、現代に通ずる喫茶の習慣もこの時期に伝わります。茶と菓子が一緒に供されるのは、現存する資料でたどると14世紀頃成立の『喫茶往来』【辰-44】辺りからとされます。
1) 慈俊『慕帰絵々詞』【ん-169】
これは本願寺第三世覚如の生涯を描いた『慕帰絵々詞』の一場面で、14世紀中頃の南北朝時代の歌会の様子を伝えます。廊下を挟んで裏の厨房では、その後の茶会の準備の真っ最中です。廊下を歩く僧の両手には大きな盆が見られ、ここに盛られているのが茶菓子だとされています。当時の茶菓子については不明な点が多いのですが、16世紀の戦国時代の茶会の記録から類推すると、果物や結び昆布などが盆に盛られて供されたと見られています。
また、僧侶が持ち帰り、その後の和菓子に繋がる食文化ということでは「点心」に触れない訳にはいきません。中国では定時以外の軽食を点心と呼んだのですが、基本的に朝夕二食の当時の日本に伝わると、点心はその間の軽い昼食として広まることとなりました。同時にこの言葉は特定の料理を指すこともあり、玄恵の『庭訓徃來』【WA16-69】には点心として羊羹、饂飩(うどん)、饅頭などの名が並びます。羊羹や饅頭は、今や和菓子の横綱格とも言える存在ですが、もとはこの時代に点心として伝来したものでした。
とはいえ、軽食として伝わった当初の饅頭は現在の甘い和菓子とは異なる料理で、餡もなく甘いものでもなかったと想像されています。食事の作法についても細かに記されている室町時代の礼法書『宗五大双紙』【127-1】 所収の図を見ると、箸が添えられ、椀に入った小振りな饅頭3つが汁・酢菜とともに出されており、料理としての饅頭の存在を伝えています。
『職人歌合画本』【よ-12】 には室町時代の饅頭売りの姿が描かれていますが、同書では「さたうまんぢう(砂糖饅頭)、さいまんぢう(菜饅頭)、いづれもよくむして候」とうたっています。菜饅頭とは野菜餡が入った饅頭、いわば野菜を使った中華饅頭であり、食事としての点心そのものです。対して砂糖饅頭はその名の通り砂糖を使った甘い饅頭と思われ、和菓子の饅頭の原型だとされています。こうして少しずつ点心から菓子へ変貌していったのです。
蜜月であった和菓子とポルトガル
和菓子文化の成立にポルトガルの存在は不可欠です。
大航海時代には、貿易やキリスト教布教のためにポルトガルなどから商人や宣教師が来日します。彼らは同時に西洋の菓子文化も持ち込みましたが、その代表格はカステラでしょう。西洋の菓子文化は、それまでは宗教的な禁忌から鶏卵を食べることのなかった日本に転機をもたらしました。基本的に植物由来の原料から作られる和菓子にあって、鶏卵の使用は唯一の例外とされています。
和菓子と言えば甘いもの、そんな現代の常識の淵源にもポルトガルは関わっています。そもそも強い甘味をもつ砂糖は貴重な輸入品で、室町時代までは、蜂蜜や蔓草から採った甘葛、米などの穀実から作った水飴が主たる甘味料という時代です。そうしたなかで、南蛮貿易時代にポルトガル船を介して砂糖が継続的に輸入され始め、江戸時代に入ってから後も唐船やオランダ船を通じて砂糖輸入量は拡大していきました。加えて琉球産の黒砂糖、讃岐国等で生産され始めた国産砂糖「和三盆」等の流通により、江戸時代には庶民の間にも貴重な砂糖の甘さを享受できる社会が到来します。前代にあってその端緒を開いた立役者こそポルトガル商人でした。
琳派様のファッショナブルなデザインに
江戸時代に入り、和菓子は「百菓」繚乱の時代を迎えます。個々の菓子に「銘」が付けられ始めるのも慶長・寛永年間頃(1596-1644)からで、元禄年間(1688-1704)の頃には琳派芸術の影響も受け、古典文学や四季折々の風情が菓子の意匠や銘のなかに取り込まれます。後世に菓子屋から出された見本帳である『御蒸菓子図』【を二-85】 には、斬新なデザインとともに「峯の曙」などの銘をもつ菓子の図柄が見られます。こうした銘やデザインについては、コラム「和菓子デザイン5選」で紹介します。
駄菓子も和菓子~飴売りの世界~
江戸時代には、庶民の間で駄菓子文化が花開きました。こうした駄菓子文化も和菓子文化の一部分だと言えましょう。ここでは、駄菓子のなかでも飴について取り上げます。江戸時代の飴は現代のものと少し異なり、稀少な砂糖よりも、穀物由来の甘味料を主原料にしたとされます。そのような飴を売る商人の諸相は、追って紹介する個性的な飴売りの存在も手伝って多くの資料に残されています。
目黒の飴屋
目黒では飴が名物の一つとされ、川口屋や桐屋といった飴屋が有名でした。 『江戸名所図会』【839-57】には「目黒飴」の桐屋が紹介されています。江戸近郊の目黒不動尊(瀧泉寺)は当時の行楽地で、ここを訪れた参詣者が土産として買い求めました。店頭には大きな桐の紋が見え、暖簾には桐屋という号が見えます。
この桐屋の号と桐の紋は、飴屋のシンボルとしても有名であったようです。菓子が登場人物の絵物語『名代干菓子山殿』【208-792】に出てくる茶屋の場面には、よく見ると暖簾には桐の紋、そして屋号「きりや」とあります。これも「飴の桐屋」というイメージと重ね合せた演出でしょう。
2) 豊国「飴うり千太郎」越嘉,文久1(1861)(『東錦絵』所収)【寄別8-5-2-3】
これは鎌倉節飴売り(後述)に扮した歌舞伎役者・第13代市村羽左衛門を描いた豊国の錦絵で、その衣装には橘と渦巻の紋様が見られます。先述の桐の紋と並んで飴屋のシンボルとして知られたのが渦巻の紋様でした。江戸時代後期に江戸の風俗についてまとめた『守貞謾稿』【寄別13-41】でも、「江戸飴店には必ず渦を描けり、今担い売りにもこれを描くものあり」と紹介しています。橘と渦巻はもともと市村家の家紋でもありますが、ここでは渦巻が飴屋のシンボルマークと重なって映ります。
傘の下商人
桐屋のように表通りに店舗を構えて飴を売る者がいる一方で、小規模な飴売りも数多く存在しました。
『守貞謾稿』【寄別13-41】によれば、「傘の下商人」という路傍の商人が三都に見られます。かれらは人通りの多い場所に大傘を立て、その下で飴などを商いました。傘を差すのは日光で飴が溶けたり、急な雨で濡れたりしないようにするためだといいます。それを描いたと見られるのが『どうけ百人一首』【208-240】という作品のなかの絵で、絵の人物も飴らしきものを売っています。また、商品台の前には、少し字が切れていますが「川口屋」と書かれています。
この川口屋という屋号は、安永年間(1772-1781)には先の桐屋と並んで飴の二大ブランドであったようで、『武江年表』【213.6-Sa222b】 には目黒の桐屋と雑司ヶ谷の川口屋が流行りであったと紹介されています。江戸幕府が編纂した江戸の地誌である『御府内備考』【593-8】によれば、正徳年間(1711-1716)に鬼子母神の境内で手製の飴を売る者が現れ、それが思いのほかに流行し、川口屋という号を名乗るようになったところ、関係のない家までが川口屋と称して飴売りを始めたとされます。『絵本江戸みやげ』【わ-54】に描かれた両国橋の袂にも川口屋の飴屋が描かれており、飴といえば川口屋、というイメージが普及していたことがうかがえます。
飴売り芸人
行商の飴売りのなかには単に飴を売って歩くのではなく、客寄せのために女装をしたり、からくり人形を披露したり、様々な工夫で差別化を図ろうとする者もいました。
英一蝶(はなぶさいっちょう)(1652-1724)の『英一蝶画譜』【京-9イ】には、江戸時代中葉の18世紀初頭に現れたと見られている「唐人飴売り」の絵が描かれ、西洋風の衣装をまとった飴売りが子どもたちと踊っています。飴売りの右側にみえる箱は客寄せ道具の「覗きからくり」で、異国の風景などを絵画や人形を使って見せるからくり装置です。飴売りの左側にあるのが、飴が入った桶で、彼らは水飴やそれを煮詰めた地黄煎(じおうせん)飴を売ることが多かったそうです。
続いて江戸時代後期の唐人飴売りです。アジア風の装いで、「あんなんこんなん」とよくわからないことを面白可笑しく歌って人気を集めました。後には替歌まで登場し、街中には真似して口ずさむ子ども達もいたそうです(『近世商賈尽狂歌合』【丑-44】)。
このように一人の飴売りのパフォーマンスが巷のブームを呼ぶことは他にもありました。有名なのが鎌倉節の飴売りです(『江戸府内絵本風俗往来』【249-50】)。嘉永年間(1848-1854)、辻々で三味線片手に弾き語りをする飴売りが現れ、「一度荷をおろすや二度び上げる暇なく、続々唄の望み絶えず」という盛況振りであったそうです。これを聞きつけた第13代市村羽左衛門(のちの第5代尾上菊五郎)は、飴売りを自宅に招いてこれを会得、市村座で演じて好評を得ています。飴売りは市村家の紋所が入った衣装を贈られ、以後はそれを着て商売に出たとされますが、絵のなかの飴売りもきちんと橘と渦巻という市村家の紋所入り衣装を着ています。なお、先に紹介した渦巻紋衣装の役者絵『飴うり千太郎』は、この鎌倉節飴売りに扮した市村羽左衛門でした(『飴うり千太郎』【寄別8-5-2-3】)。
いつしか違うお菓子も売り歩き
菓子類を荷ひ商ふこと、水飴、桜飴などの外には持来る事なかりしが、今は其数ふへて、干菓子はもちろん、まんぢう、ようかん、外良(ういろう)餅、いろいろの菓子類をうりあるく事となれり
これは寛政年間頃(1789-1801)の随筆『梅翁随筆』【US1-E7】の記述です。昔は行商の菓子売りと言えば専ら飴売りであったものが、その後は種類が増えて、干菓子はもちろんのこと、饅頭や羊羹など色々な菓子を売り歩くようになったと述べています。この時代には既に、行商の菓子売りを介して、多様な和菓子が市井の人々のもとに届けられていたのでしょう。
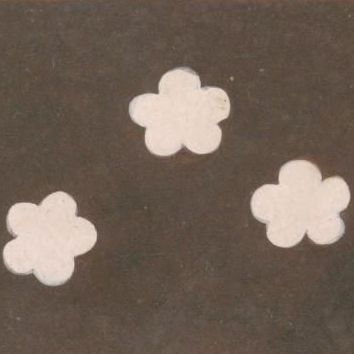
次へ
コラム 和菓子デザイン5選