- 本の万華鏡
- 第19回 白瀬矗、南極へ―日本人初の極地探検
- 第1章 白瀬隊・南極への旅
第1章 白瀬隊・南極への旅
「其の極(きょく)遂に北極探検は断念して、正反対なる南極に突進せんと欲した。」
日本人で初めて南極を目指した白瀬隊。その隊長である白瀬矗(しらせのぶ)が南極行きを志したのは、明治42(1909)年9月のことでした。
第1章では白瀬矗が南極行きを決めた日を起点に、白瀬隊の南極探検を追いかけます。
※本章では特に言及がない限り、節タイトル及び「」部分は白瀬矗『南極探検』【297.9-Sh85ウ】の本文より引用。
1) 白瀬矗『南極探検』博文館,大正2【297.9-Sh85ウ】
探検隊長であった白瀬矗の記した南極探検の本です。白瀬本人の生い立ちから南極探検の顛末まで、何を思いどう行動したのかが、豪胆な性格そのままの勇ましい文体で自由に書かれています。 南極探検の際に撮影された写真も収録されており、船の様子や隊員達の雰囲気なども確認することができます。
2) 南極探検後援会編『南極記』南極探検後援会,大正2【297.9-N627n】
白瀬隊の南極探検を支援した後援会がまとめた資料です。南極探検の顛末のほか、学術調査の内容などをまとめており、白瀬隊の南極探検をより客観的に見つめることができます。
光陰一刻値千金!
明治42(1909)年9月8日 決意
白瀬隊の隊長である白瀬矗は、幼い頃から冒険譚に親しんできたこともあり、北極探検を強く志望していました。しかし明治42(1909)年9月8日、同年4月にアメリカの探検家ロバート・ピアリー(Robert Edwin Peary)が北極点を制覇したとの報道が飛び込んできます。白瀬はひどく落胆しますが、北極点が制覇されたなら次は南極点だと急に目標を180度変更、当時、同じく南極点を目指していた英国のロバート・スコット(Robert Falcon Scott)率いる探検隊と競争だと意気込みます。
―「光陰一刻値千金(こういんいっこくあたいせんきん)!」
一刻も早く出発したい白瀬。しかし、同行する隊員はおろか資金もありません。そこでまず、知己を頼り帝国議会に南極探検経費の支給の請願をするところから活動を始めます。
この請願(第26回帝国議会衆議院請願第1994号)は、両院とも通過し政府へ送付されました。しかし請願には実効性がないため、当初希望した10万円はもちろん、貴族院で示された3万円についても、ついに支給されることはありませんでした。ちなみに、当時の帝国議会の予算書によれば10万円なら大学、3万円なら専門学校の設立資金としているようですから、白瀬の希望した額はかなり膨大なものではあったようです。
ゆけないと思ふ人には眞實ゆけぬであろう
明治43(1910)年7月5日 南極探検発表演説会の開催
民間からの寄附によって資金を調達しようと考えた白瀬は、交流のあった村上濁浪(むらかみだくろう)(俊蔵)に援助を求めます。村上は、『冒険旅行術』大学館【96-45】 などの著書がある人物で、当時『探検世界』【雑19-120】を発行していた成功雑誌社の社長でした。彼は白瀬に「南極探検発表演説会」の開催を助言します。その助言どおり明治43(1910)年7月5日に行われた演説会は大盛況となり、同日中に村上を中心として三宅雪嶺(雄二郎)・東北学院創立者の押川方義(おしかわまさよし)ら6人を幹事、大隈重信を会長とする「南極探検後援会」が設立されることとなったのです。
また、演説会後は、隊員や寄贈による探検の装備なども集まり始めました。新聞社も白瀬隊への援助を行うキャンペーンを展開し、寄附などを募るようになります。この後も、白瀬隊の旅が終わるまで国内では後援会の協力のもと支援のための相撲興行、演劇、唱歌の作成などが行われました。
ところが、用船問題をはじめ多くの問題が重なり出発予定日は何度も延期となります。やがて、南極行きを疑問視する声も上がり始めました。
―「恁那事(こんなこと)をしてゐる中(うち)に一刻千金の星霜は容赦なく経つ、反之(これにはんして)スコット大佐は一分一秒と南極に迫る。自分達が徒(いたず)らに船の詮議(せんぎ)をしてゐる中(うち)に大佐は無人境を快心の笑みを以(もっ)て航行してゆく」
それでも諦めず南極を志す白瀬達。紆余曲折を経て、最終的に手に入った寄附金は約4万円。この時、スコット率いる英国探検隊の資金は約40万円であり、その10分の1の資金ではありましたが、これに後援会名義の借金などを加え、なんとか出航の準備を整えます。
行けよ開南丸
明治43(1910)年11月29日 旅立ち!
漁船を整備しなおした小さな船「開南丸(かいなんまる)」にソリ用の犬や食料を詰め込み、白瀬隊27人は芝浦埋立地(現在の芝浦ふ頭)を出港しました。
一路、南を目指す開南丸と白瀬隊。赤道付近の暑さや狭い船内でのストレスからか多くの犬を失いながらも旅を続け、ニュージーランドのウェリントン港を経由し、明治44(1911)年3月初頭、ついに南極圏に突入します。
―「片吟鳥(ぺんぎんちょう)!氷山!氷河!是(これ)から見るもの聞くもの凡(すべ)て奇であらう。異であらうと思つた」
日本とは季節が反対の南極。12月から1月という短い夏を終え、すでに季節は秋、そして長い冬へと向かいつつありました。船首で氷を砕きながら、南極圏を突き進む開南丸でしたが、3月9日前後に氷盤に囲まれ身動きが取れなくなってしまいます。たまたま良い風が吹き、その場から脱することは適いましたが、それ以上進むことはできないという船長野村直吉(のむらなおきち)の判断もあり、ついに一度、オーストラリアのシドニーまで引き返すことを決めます。3月14日のことでした。
この時、南極大陸には前述のスコット隊、そして急遽南極点行きを表明したノルウェーのロアール・アムンセン(Roald Engelbregt Gravning Amundsen. 本展示で紹介している資料には「アムンゼン」の表記もあります。)隊がすでに上陸しており、越冬後南極点を目指すことを表明していました。白瀬隊はここで大きく後れをとる形となり、以降、後援会の意向もあって探検目的に「学術調査」を入れるようになります。
3) 村上俊蔵書簡 齋藤実(さいとうまこと)宛 明治44年3月【<憲政資料室所蔵>斎藤実関係文書1499】
この書簡は、白瀬隊がウェリントン港を出発して南極を目指している頃、南極探検後援会の専任幹事である村上濁浪(俊蔵)が海軍大臣の斎藤実に送ったもので、南極探検への国庫補助金の支給を懇願する内容です。南極探検は大事業であるため巨額の経費が必要であり、民間の義捐金だけでは事業の達成は困難であるという記述から、資金集めに苦労している様子がうかがえます。
書簡にも記されている「南極探検ニ関スル国庫補助ノ建議案」(第27回帝国議会衆議院第104号)は、衆議院で可決されましたが、政府から補助金が支給されることはありませんでした。
<翻刻>
拝啓
春暖之侯、貴官倍々御清
穆被為在奉賀候、扨甚以テ
唐突ノ至ニ御座候得共、予テ
御承知ノ如ク、白瀬中尉一行南極
探検ノ企画ハ、朝野官民
有志諸君ノ深厚ナル同情ニ
依リ、急速ノ事ナカラ時期ノ関
係上開南丸ヲ艤装シ、昨年
十一月廿九日本邦ヲ出帆シ、五千余
哩ノ海上無恙本年二月八日
新西蘭ウェリントン港ニ着、同
十一日紀元節ノ当日ヲ以テ極地ニ
進航シ目下略ボ上陸地点ニ
達スル日限ニ相当リ候事ト存候、就テ
ハ本会ハ会長大隈伯指導
ノ下ニ於テ極力同事業ヲ援助
罷在リ、能フ可クンバ民間ノ義金
ニ依テ此事業ノ遂行ヲ為サンコト
ヲ期シ候処、何分ニモ此企画タ
ル中々ノ大事業ニテ多大ノ経
費ヲ相要シ、今後ニ於テモ船舶ノ
修繕・船員ノ給料・隊員家族
扶助料・新西蘭滞在費等
巨額ノ費用ヲ支弁セザルベカラ
ザル儀ニ付、到底義金ノミニテハ
此事業ノ貫徹ヲ期スルニ困難
ナルノ有様ニ有之候事故、此際政
府当局諸士ノ御賛成ヲ仰ギ
度奉懇願候、此儀ニ付テハ先日
大隈伯ヨリ直接桂首相ニ宛テ
陳情書差上有之、今回又モ国民
ノ代表者タル代議士諸氏ヨリ
南極探検ニ関スル国庫補助
ノ建議案ヲ衆議院ニ提出
致サレ候得共、此国庫補助
ノ儀ハ申ス迄モナク政府当路
者諸君ノ御賛成ヲ得ルニアラザ
レバ目的遂行難致次第ニ付、
貴官ニ於テモ本会ノ趣旨ヲ
諒トセラレ補助金御下附被下
候様御配慮相煩度奉懇願候、
実ハ参堂拝顔ノ上御願致度
存候得共、国務御多端ノ折
柄故、態ト遠慮仕リ書中
愚意申述候、宜シク御酌取
奉希候、敬具
三月
専任幹事
村上俊蔵
海軍大臣男爵斎藤実殿
今秋解氷の機を以って再擧を企てん
明治44(1911)年3月15日~11月19日 シドニー滞在
シドニーまで船を戻した白瀬隊。ここで彼らは、一度日本へ戻る組とシドニーで半年近く生活する組に分かれます。
日本へ戻ったのは、船長の野村と書記長の多田恵一(ただけいいち)達。日本滞在中、彼らは後援会への報告や資金の追加調達などに駆け回ります。
一方、シドニーに残った隊長の白瀬達も、現地にいる日本人達と連絡を取り合い、生活に苦労しながらも情報収集に努め、次の旅への英気を養いました。
4) 河岡潮風(かわおかちょうふう)(英男)『五々の春』博文館,明治45【332-278】
著者の河岡は冒険小説を複数冊著した人物で、一時帰国した多田恵一の演説の旅に論客として同行しました。随筆集の体裁を取った本書には、その時の日記や講演の内容、南極探検隊の詩などが収録されています。
河岡は関西方面の旅のみ同行したようですが、文末に「南極探検遊説は病躯(びょうく)がいか程迄(まで)の劇務に堪(た)ゆるかを実験するよき試金石であった」「二十五日間二千五百二十七哩餘(まいるよ)の旅、演説二十回、聴衆一萬(いちまん)と號(ごう)する」とあり、病気を抱えながらも、ハードなスケジュールをこなしていたことが見てとれます。
なお、タイトルの「五々の」とは、五々二十五、河岡の25歳を記念して出版したためにつけられたものですが、本人は本書の出版直後、脳膜炎により夭折しています。
日本とシドニー。遠く離れた地ではありますが、どちらも再度南極を目指すために活動する白瀬隊。隊員や失った犬の補強を終え、ついに再挙の日がやってきます。
-「一回の失敗既に業(すで)(原文ママ)に無念骨髄(こつずい)に徹っす。第二回にして努力せずんば何の貌(かんばせ)あつてか故国の土を踏まん」
明治44(1911)年11月19日、開南丸は船首をシドニー港から南へと向け出航しました。
南緯八十度五分・最早一歩も前進する克はず
明治45(1912)年1月28日 旅の終着地へ!
シドニー港を旅立った白瀬隊は、順調に航海を重ね、再び南極圏に入ります。
―「噫(ああ)南大陸よ!多年憧憬(あこが)れたる南大陸よ!」
明治45(1912)年1月16日。白瀬隊はついに、ホエールズ湾において船を南極大陸に寄せることに成功、ここを拠点として陸上探検隊と沿岸探検支援隊(以下、「沿岸隊」という。)とに分かれ、順次南極点到達と探索の準備を進めます。
-「あゝ前後三年の苦心惨憺(くしんさんたん)其の効果空しからず首尾よく南大陸に足跡を印(しん)(原文ママ)せし愉快」
-「あゝ忘る可(べ)からず明治四十四年(原文ママ)一月十六日!」
停泊中、沿岸隊は周辺の探索や学術調査を行う傍ら、ちょうど時を同じくしてホエールズ湾に停泊していたアムンセン隊と交流を持ちます。
―「往(ゆ)かん往かん往け往け」
1月19日。陸上探検隊から分離した白瀬率いる5人の突進隊は、いよいよ南極点にソリを向けました。
過酷な南極の世界。突進隊の旅は想像していた以上に困難を極めましたが、極地探検という稀有な体験を心の支えとし、彼らは先へ先へと歩を進めていきます。
―「四顧只白皚々(しこただはくがいがい)目に入るもの皆寒さう雪が深いので時々橇(そり)が埋没しさう」
―「あゝ氷上の天幕!天幕内の一夜!・・・・・世にこの位珍らしい就眠はなからう」
しかし、1月28日、南緯80度5分西経154度の地点で寒さと食料不足により、ついに白瀬隊は力尽きます。
―「然(しか)るに南緯八十度五分西経百五十四度に到るや一歩も進む能(あた)わず。進まんか死せん耳(のみ)、否、死は兼て期せるところ敢(あえ)て惧(おそ)れざれども使命は死よりも重し。死しては命を果たすを得ず。我は泣いて使命の為にこの上の行進を中止しぬ。更に進まんか猪勇而耳(ちょゆうのみ)」
白瀬はここに日本国旗を立て、一帯を大和雪原(やまとゆきはら)と名付けることとし、引き返すことを決めます。
こうして、白瀬率いる突進隊は翌日沿岸方面へ引き返し、2月4日沿岸隊と合流、帰国することを全隊員に告げたのでした。
富士の姿を打ち眺めた時の一同の狂喜
明治45(1912)年6月20日 旅の終わり
南極を発った白瀬隊は3月23日、再びウェリントンに入港します。隊長の白瀬ら数人はここで隊を離れ連絡船で先に帰国、残りの隊員は開南丸で4月2日にウェリントン港を出て6月20日に芝浦埋立地へ帰港、盛大な出迎えを受けました。帰国した喜びをそれぞれにかみしめる隊員達。ここに日本人初の南極探検は終わりを告げます。
―「不肖等(ふしょうら)今回の探検を了し畢(おわ)つて多少なりしも歐米に向つて日東國(にっとうこく)の名聲(めいせい)を揚げたりとせばそは我等の努力に非ず。満天下諸彦(しょげん)の應援(おうえん)の賚(たまもの)に歸(き)せずんば非ざる也」
探検を企画してから日本へ戻ってくるまで実に3年近く、そのうち南極大陸への上陸期間は僅か20日程度のものでした。そしてこの後、日本の南極探検史は国際地球観測年である昭和30(1955)年に南極観測参加の意思を表明するまで空白の時期が続きます。
探檢の効果は皆無ならざるを断言せんと欲す
明治45(1912)年~ 白瀬隊の影響
昭和32(1957)年から33(1958)年にかけて第一次南極地域観測隊越冬隊長となった西堀栄三郎(にしぼりえいざぶろう)は、その著書『南極越冬記』【297.9-N739n】の「京都にて」という節でこんなことを記しています。
「わたしは十一歳、京都の明倫小学校の生徒だった。ちょうど、白瀬中尉が南極探検から帰って来られて、一、二年たったあとだったとは思うが、四条の南座で、その探検報告と映画の会があった。(中略)小さな開南丸が雄々しく進んでいくのを見て、非常な感動をうけたのを覚えている。そのとき以来、南極がわたしの心の中にすみついてしまったのであった」
ほかにも、白瀬隊が南極において名付けた「大隈湾」「開南湾」といった地名は後に国際的な名称として認められ現在でも残っています。白瀬隊の旅は、当時の人々はもちろん、その後に続く南極探検の礎となったといえるでしょう。
5) 嵩山堂編輯局編『分邦詳密万国大地図』青木嵩山堂,明治40【89-142】
6) 武田輝太郎製『新撰南極地図』南極探検学術研究部,大正1【89-185】

次へ
補章 南極を目指した人々
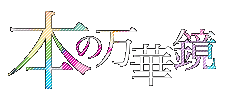






![朝日新聞[東京] 朝日新聞[東京]](/kaleido/entry/19/img/06.jpg)












