温湿度管理
一般に、図書館資料の劣化や虫菌害を抑制するためには、低温低湿で変動のない環境で保存することが望ましいとされています。「低温低湿」についてはさまざまな考え方がありますが、恒常的に湿度が65%を超えるようになるとカビが発生する確率が高まると言われているので、湿度65%を1つの目安として考えることができます。同時に書庫内で作業する人の作業環境にも気を配る必要があります。紙資料、マイクロフィルムを中心とした温湿度管理の基礎的な知識については、こちらをご覧ください。
- 第24回保存フォーラム「持続可能な環境管理-図書館・文書館の資料を中心に-」
- 東京文化財研究所 佐野千絵氏講演「書庫・収蔵庫の温度湿度管理」(PDF: 336KB)
変動のない低温低湿な書庫環境を実現するもっともシンプルな方法は、一定の低温低湿の設定で空調機を動かし続けることです。しかし、昨今の二酸化炭素の削減や節電への対応の必要性から、省エネルギーでコストパフォーマンスの良い持続可能な空調機の運転が求められています。
国立国会図書館の書庫では、温度と湿度を制御できる空調機を設置しており、書庫内の温湿度をこまめにチェックし、「書庫内で人が作業できる温度」「65%以下の湿度」を目指し、1年間を通じて、また1日の中でも、温湿度を急激に変動させないことを目指しています。また、閲覧室との温湿度差ができるかぎり小さくなるようにも心がけています。
ここで、温度と湿度の関係について説明します。湿度は温度の変動に連動する性質をもっています。そのため温湿度管理を考える際にはこれら2つを分けて考えるのではなく、一緒に考えるとより効果的です。連動の仕組みを見ていきましょう。湿度は次の計算で求めることができます。
![]()
分母にあたる「一定空間における飽和水蒸気量」(その空間に含むことのできる最大水蒸気量=湿度100%の時の水蒸気量)は、温度が高くなれば大きくなり、温度が低くなれば小さくなります(下表参照)。
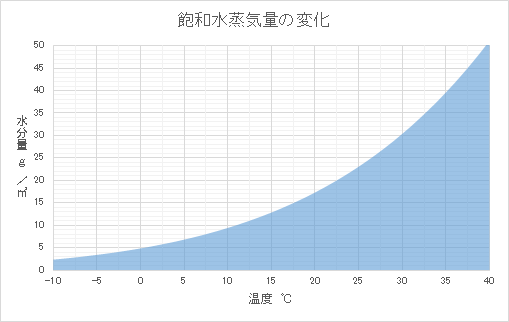
つまり、上記の計算式で分子にあたる「一定空間における水蒸気量」が変化しないならば、温度が高いほど分母にあたる飽和水蒸気量が大きくなるため、相対的に湿度は低くなります。
反対に、分子にあたる一定空間における水蒸気量が変化しないならば、温度が低いほど分母にあたる飽和水蒸気量が小さくなるため、相対的に湿度は高くなるのです。
温湿度管理の一例として、国立国会図書館東京本館の夏の空調機の運転方法をご紹介します。日本の夏は暑くてジメジメする高温高湿です。資料の理想の保存環境である低温低湿からかけ離れており、一年を通じて一番気を使う季節です。
まず、梅雨の時期、書庫内の湿度が60%を超える頃から空調機の運転を開始します。夏本番が近付き、外気の温湿度が上がると書庫全体の温湿度もさらに上がってくるので、設定温度を徐々に上げることで湿度の上昇を抑えます。夏の盛りには、通常、空調機の運転を止めている夜間にも送風のみの運転を行い、湿気が局所的に溜まらないよう、書庫内の空気を循環させています。
下のグラフは2013年夏の書庫内と外気の1日の平均温湿度を比較したものです。先に述べた考え方で空調機の運転を実施したところ、書庫内の温湿度は乱高下することなく比較的穏やかな変動に収まりました。
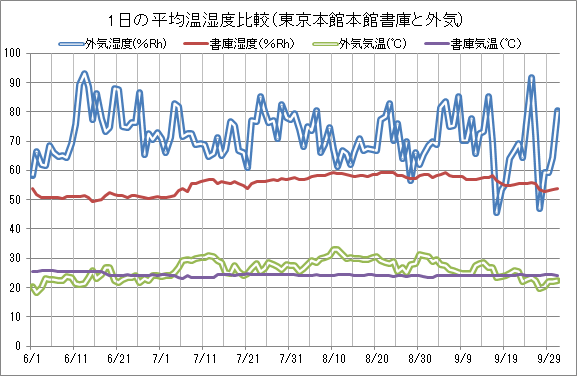
なお、この事例はあくまでも国立国会図書館東京本館の環境・設備で実施した結果です。最適な空調運転方法は施設の環境や設備によって異なりますので、ご注意ください。
また、より効果的に温湿度を管理するために、書架の最下段と床の間をできるかぎり空けて床からの温度・湿度の変化を直接受けないようにしています。
温湿度測定
書庫内の温湿度の計測には、書庫空調管理システムと任意の場所に設置できるコンパクトなデータロガーを併用しています。書庫空調管理システムで書庫内全般の温湿度を監視・制御をし、カビの生えやすい資料、高温高湿に弱い資料の周りなどピンポイントでの監視が必要なところにはデータロガーを設置するというように使い分けています。

データロガー
温湿度を計測し数値データを記録する機械