- 本の万華鏡
- 第30回 天下タイ平~魚と人の江戸時代~
- おわりに・参考文献
- はじめに
- 第1章 とりタイ!
- 補章 鯨とのお付き合い
- 第2章 売りタイ!
- 第3章 食べタイ!
- おわりに・参考文献
- 付録 魚介類難読漢字クイズ
おわりに
漁業、商売、食事など、人と魚の関わりには様々な側面があります。そして、その大部分は江戸時代に大きく発展して人々の生活を豊かにし、現在につながっていると言えるでしょう。
しかし、日本の魚介類消費量は、近年減少が続いています。魚は古くから日本人とともにあり、その身体、生活、文化をつくってきました。
また、2022年は国連により「零細漁業と養殖の国際年」に制定されており、世界的にも地域の漁業の持続可能性について考える機会が増えることと思われます。
当館の資料を通して、皆さんが魚の魅力を再発見していただければ幸いです。
本文中で紹介したものの他にも、江戸の人々と魚の関わりを知ることのできる資料はたくさんあります。国立国会図書館電子展示会「錦絵でたのしむ江戸の名所」では、潮干狩りや魚市場の様子などを、キーワード・地名ごとに一覧することもできます。
次のページに、国立国会図書館の資料と魚について、さらに知ることのできる付録を用意しました。ぜひお楽しみください!
参考文献
全体
- 蟻川トモ子『江戸の魚食文化 : 川柳を通して』(雄山閣アーカイブス 食文化篇), 雄山閣, 2017.1【GD51-L162】
- 大阪府文化財センター編『天下の台所大坂 : 魚食文化の歴史を探る』,大阪府文化財センター, 2012.3【GD51-L4】
- 鈴木克美『鯛』(ものと人間の文化史 69), 法政大学出版局, 1992.10【RB821-E61】
- 冨岡一成『江戸前魚食大全 : 日本人がとてつもなくうまい魚料理にたどりつくまで』, 草思社, 2016.5【GD51-L134】
- 原田信男編著『江戸の料理と食生活:日本ビジュアル生活史』, 小学館, 2004.6【GD51-H55】
- 『完全保存版江戸の食と暮らし : 和食の原点は江戸にあり』(洋泉社MOOK), 洋泉社, 2016.9【Y94-L31440】 データベース「JapanKnowledge」より『国史大辞典』、『日本国語大辞典』、『日本大百科全書(ニッポニカ)』
第1章 とりタイ!
- 秋山高志ほか共編『図録山漁村生活史事典』, 柏書房, 1981.8【GD11-74】
- 大島暁雄ほか編『図説民俗探訪事典』, 山川出版社, 1983.4【GB8-109】
- 大島建彦ほか編『日本を知る事典』, 社会思想社, 1994.5【GB8-G15】
- 笹間良彦『復元江戸生活図鑑』, 柏書房, 1995.3【GB374-E31】
- 田辺悟『網』(ものと人間の文化史 106), 法政大学出版局, 2002.7【RB731-H1】
- 福田アジオほか編『精選日本民俗辞典』, 吉川弘文館, 2006.3【GB8-H55】
第1節 魚介を追う技
- 荒居英次『近世の漁村』(日本歴史叢書新装版), 吉川弘文館, 1996.2【DM674-G1】
- 棚橋正博・村田裕司編著『絵でよむ江戸のくらし風俗大事典』, 柏書房, 2004.10【GB371-H13】
- 長辻象平『江戸の釣り : 水辺に開いた趣味文化』(平凡社新書), 平凡社, 2003.4【KD984-H13】
- 林英夫・青木美智男編集代表『しらべる江戸時代:事典』, 柏書房, 2001.10【GB341-G102】
- 山口和雄『日本漁業史』, 東京大学出版会, 1957【660.21-Y258n】
- 山口徹『近世漁民の生業と生活』, 吉川弘文館, 1999.2【DM674-G15】
第2節 大漁を願って
- 大塚民俗学会編『日本民俗事典』, 弘文堂, 1972【GB8-21】
- 民俗学事典編集委員会編『民俗学事典』, 丸善出版, 2014.12【GB8-L21】
- 柳田国男編『海村生活の研究』, 日本民俗学会, 1949【384.1-Y529k】
- 吉井良隆編『えびす信仰事典』(神仏信仰事典シリーズ 2), 戎光祥出版, 1999.3【GD33-G301】
補章 鯨とのお付き合い
- 森弘子・宮崎克則『鯨取りの社会史:シーボルトや江戸の学者たちが見た日本捕鯨』, 花乱社, 2016.5【DM653-L15】
- 東京都品川区口碑伝説編集委員会編『品川の口碑と伝説』, 品川区教育委員会, 1958【388.136-To458s】
- 山下渉登『捕鯨1』(ものと人間の文化史 120-1), 法政大学出版局, 2004.6【DM653-H29】
- しながわ観光協会「利田神社・鯨塚」<https://shinagawa-kanko.or.jp/spot/toshidajinja/>
第2章 売りタイ!
- 松下幸子『図説江戸料理事典』, 柏書房, 1996.4【EF27-G361】
第1節 おいしく保存する工夫
- 矢野憲一『魚の文化史』(講談社学術文庫 2344), 講談社, 2016.1【GD51-L114】
- 歌舞伎座「江戸食文化紀行 -江戸の美味探訪- NO.61 江戸の海苔」<https://www.kabuki-za.com/syoku/2/no61.html>
- 「伊勢神宮献上!熨斗あわびの里 海女発祥の地 国崎神戸」<http://www.kuzaki.net/index.html>
- ふくいドットコム「若狭かれい」<http://www.fuku-e.com/200_gourmet_calendar/20_wakasakarei/>
第2節 魚市場の賑わい
- 槌田満文編『江戸東京職業図典 : 風俗画報』, 東京堂出版, 2003.8【GD11-H42】
- 本渡章『大阪名所むかし案内 : 絵とき「摂津名所図会」』, 創元社【GC161-H64】
- 「えんぎもの(32) 初鰹」『七緒 : 着物からはじまる暮らし』vol.42, プレジデント社, 2015.6【Y94-L21236】
コラム 生産地から消費者へ
- 高橋幹夫『江戸あきない図譜』新装版, 青蛙房, 2015.12【DC48-L26】
- [東京都]江戸川区教育委員会社会教育課編『古文書にみる江戸時代の村とくらし 2 (街道と水運)』(江戸川ブックレット 8), 江戸川区教育委員会, 1991.3【GC67-E74】
- 林宏『鯖のはなし : 大衆魚「鯖」の、知られざる輝かしい経歴』, クイックス, 2011.9【RB821-J63】
- 樋畑雪湖『江戸時代の交通文化』, 臨川書店, 1974【DK7-68】
- ジャパンサーチ「北前船」<https://jpsearch.go.jp/gallery/ndl-DQ89R33j37fE4vM>
- 東京学芸大学附属図書館「電子展示:寺子屋の学習と往来物」<https://library.u-gakugei.ac.jp/digitalarchive/oraidenshitenji_1.html>
第3章 食べタイ!
第1節 食された魚介類
- 江原絢子・近藤惠津子『おいしい江戸ごはん』, コモンズ, 2011.11【Y73-J3434】
- 狩野博幸監修『江戸の動植物図譜』, 河出書房新社, 2020.3【RA55-M6】
- 車浮代『江戸の食卓に学ぶ : 江戸庶民の"美味しすぎる"知恵』(ワニブックス|PLUS|新書 140), ワニ・プラス, 2015.6【GD51-L86】
- 原田信男校註解説『料理百珍集』新装版, 八坂書房, 2009.12【EF27-J432】
- 原田信男『江戸の食文化:和食の発展とその背景』, 小学館, 2014.5【GD51-L50】
- 吉井始子編『江戸時代料理本集成 : 翻刻』第2巻, 臨川書店, 1978.12【EF27-J444】
- 下村道子ほか「江戸時代の魚介類料理の特徴--『料理物語』の分析から」『大妻女子大学家政系研究紀要』(43), 2007.3【Z22-293】
- 松下幸子「料理書から見た江戸時代の魚介類」『食生活研究』21(3), 2000【Z6-1674】
第2節 江戸前料理
- 飯野亮一『すし天ぷら蕎麦うなぎ:江戸四大名物食の誕生』(ちくま学芸文庫 イ54-2), 筑摩書房, 2016.3【GD51-L132】
- 石毛直道『日本の食文化史:旧石器時代から現代まで』, 岩波書店, 2015.11【GD51-L115】
- 大川智彦『現代すし学 : すしの歴史と、すしの今がわかる』, 旭屋出版, 2008.1【EF27-J107】
- 大久保洋子『江戸の食空間 : 屋台から日本料理へ』(講談社学術文庫 2142), 講談社, 2012.11【GD51-J162】
- 田辺悟『鮪』(ものと人間の文化史 158), 法政大学出版局, 2012.4【RB821-J70】
- 平野正章・小林菊衛『てんぷらの本』, 柴田書店, 1976【EF27-392】
- 松下幸子『錦絵が語る江戸の食』, 遊子館, 2009.7【GD51-J54】
- 『たべもの日本史総覧』(歴史読本特別増刊. 事典シリーズ 17), 新人物往来社, 1993.1【GD51-E149】
- 芝恒男「日本人と刺身」『水産大学校研究報告』60(3), 2012.2<http://www.fish-u.ac.jp/kenkyu/sangakukou/kenkyuhoukoku/60/03_4.pdf>
第3節 関西の魚食文化
- 上田純一編『京料理の文化史』, 思文閣出版, 2017.3【GD51-L174】
- 佐藤鶴吉『日本永代蔵評釈』, 明治書院, 昭和5【603-96】
- 高橋幹夫『江戸あじわい図譜』, 青蛙房, 1995.6【GD51-E178】
- 宮本又次『大阪の風俗』(毎日放送文化双書 8), 毎日放送, 1973【GC163-7】
- 歌舞伎座「江戸食文化紀行 -江戸の美味探訪- NO.63 川魚料理と床、生簀」<https://www.kabuki-za.com/syoku/2/no63.html>
- 歌舞伎座「江戸食文化紀行 -江戸の美味探訪- NO.125 二十四孝と鯉」 <https://www.kabuki-za.com/syoku/2/no125.html>
- 歌舞伎座「江戸食文化紀行 -江戸の美味探訪- NO.241 大坂の福本ずし」 <https://www.kabuki-za.com/syoku/2/no241.html>
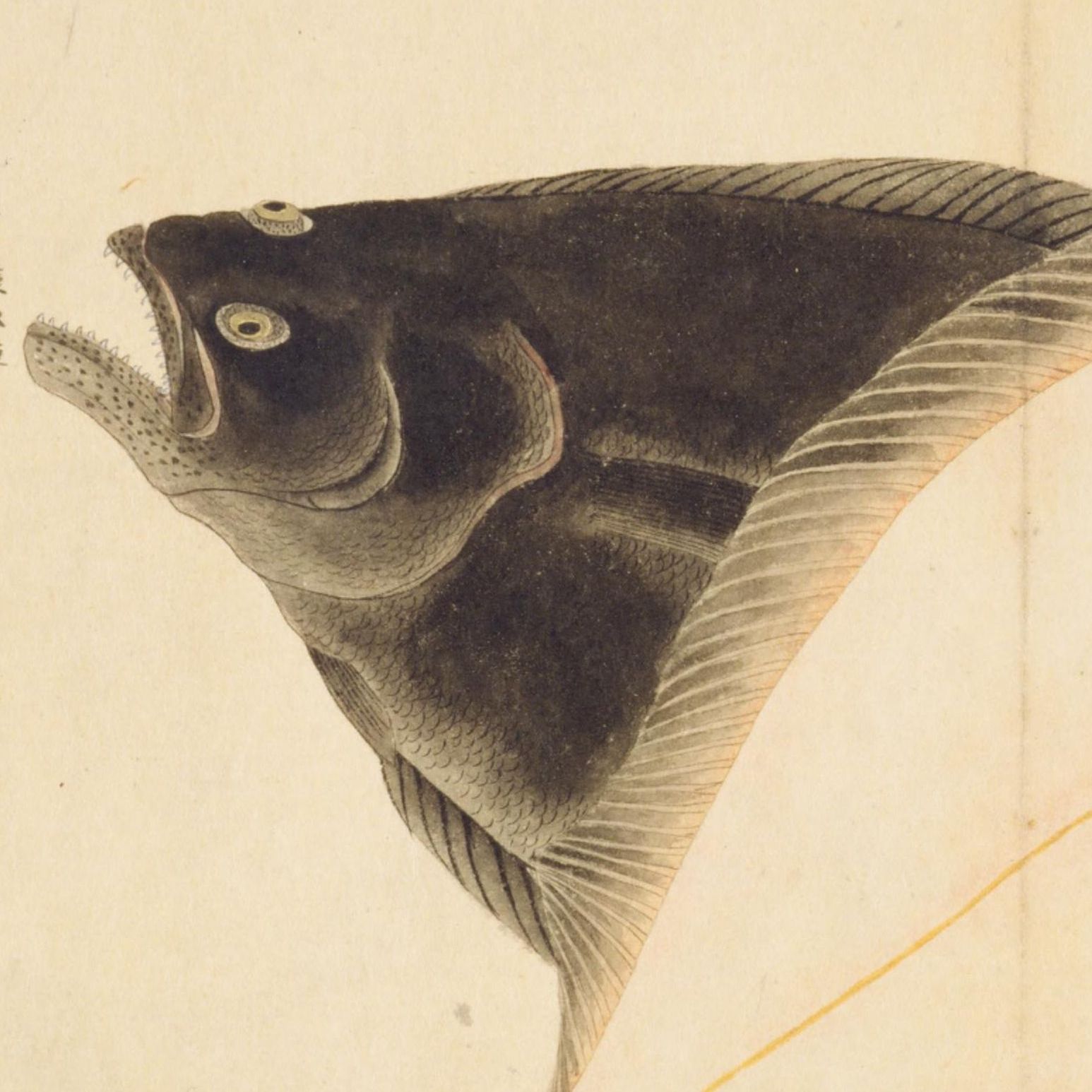
次へ
付録 魚介類難読漢字クイズ

