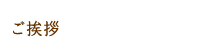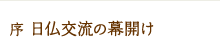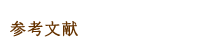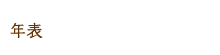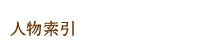![]()
3. 映画
フランスで発明されたシネマトグラフは、その後無声映画、トーキーと進化する中で、世界的に大衆娯楽の王としての地位を確立していく。日本もその例外ではない。そのため日本に輸入され公開された数多くのフランス映画の名作は他のジャンル以上に、戦前から戦後にかけて多くの日本人のフランスへの憧れをかきたてることになった。
シネマトグラフの日本初公開
映画の原型となるシネマトグラフは、1895年にフランスのリュミエール兄弟によって開発された。兄オーギュスト(1862-1954)とリヨンの工業学校の同窓であった、京都の実業家・稲畑勝太郎(1862-1949)は、明治29(1896)年に渡仏した際にシネマトグラフを見て日本での興行権を獲得し、翌年2月15日に大阪の南地演舞場での日本初興行を実現した。稲畑に同行して来日した撮影技師コンスタン・ジレル(1873-1952)は、初めて日本でのシネマトグラフの撮影を行っており、そのフィルムはリュミエール社の日本関係映像集「明治の日本」に収められている。なお稲畑は後に興行権を横田永之助(1872-1943)に譲り、後の日本活動写真会社(現日活)の源流となる。
活動写真雑誌編輯局『吾輩はフィルムである』活動写真雑誌社,大正6(1917)年【364-140】
夏目漱石(1867-1916)の『吾輩は猫である』のスタイルを借りて、フィルム自らが、撮影機やフィルムの原理や来歴などを語る体裁の本。当時の国内外の主要な役者、映画会社の紹介もある。
無声映画時代
フランスの映画産業は、その後もパテ社やゴーモン社といった映画会社によって順調に発展を続けた。この時期に作られたマックス・ランデ(1883-1925)の喜劇映画や犯罪活劇《ジゴマ》シリーズは、日本でも大人気となった。特に後者は《日本ジゴマ》のような翻案映画が次々と作られ、さらには劇中の犯罪手口をまねた事件が起きたために、当局によって上映禁止になったほどである。
1920年代のフランスでは、文学や美術におけるダダイスムやシュルレアリスムの潮流が映画にも波及し、アヴァンギャルド映画がブームになった。代表的な作品としては、シュルレアリスム映画の巨匠・ルイス・ブニュエル(1900-1983)の《アンダルシアの犬》、《黄金時代》が挙げられる。こうしたアヴァンギャルド映画は、評論家・内田岐三雄(1901-1945)らによって日本に紹介された。
内田岐三雄『欧米映画論』書林絢天洞1935【778.23-U822o】
内田岐三雄は、第一高等学校在学中に『キネマ旬報』【Z11-158】の編集同人となり、その後同誌における映画批評などで活躍した。初期の小津安二郎(1903-1963)の作品を高く評価したことでも知られる。内田は昭和4(1929)年から足かけ4年にわたりパリやニューヨークを回った。パリでは、マン・レイ(1890-1976)の《ひとで》など、当時最新のアヴァンギャルド映画などを数多く実見し、その成果が本書第一篇の「前衛映画」の中で詳しく紹介されている。
トーキーの時代
映画はいよいよトーキーの時代に突入する。フランス映画で日本初のトーキー映画は、昭和6(1931)年に公開されたルネ・クレール(1898-1981)監督の《巴里の屋根の下》であったが、仏文学者で早稲田大学教授の山内義雄(1894-1973)は、この映画でフランス女優の話すフランス語のセリフを直接聞くことができた感動を大学の授業で語ったという。
トーキーでは俳優によるセリフや対話の妙が映画表現の重要な要素として加わった。長い文学・演劇の伝統を持つフランスでは、より一層文学的、演劇的要素を強めることになり、人生の機微や人間そのものへの深い洞察に裏打ちされた作品群はその映像表現手法を含め「詩的レアリスム」と称された。1930年代のフランス映画は、ルネ・クレール、ジャン・ルノワール(1894-1979)、ジュリアン・デュヴィヴィエ(1896-1967)、ジャック・フェーデ(1885-1948)という「詩的レアリスム」を体現した四大巨匠を中心に黄金期を迎えることになる。
日本でもこうした諸作品は映画関係者や知識人をはじめ一般大衆にも広く受け入れられた。例えば、昭和6(1931)年から同14(1939)年までの『キネマ旬報』【Z11-158】の批評家投票による年間ベスト・テンにおいて、毎年フランス映画(具体的にはクレール、フェーデ、デュヴィヴィエの作品)が1位または2位(6年と8年が2位でそれ以外の年はすべて1位)を占めた。
また前述の《巴里の屋根の下》は、その挿入歌が日本におけるシャンソン流行の契機となったとされる。同8(1933)年公開の同監督の《7月14日》には《巴里祭》の邦題が付けられ、その邦題の影響で日本では現在でも7月14日の革命記念日を「パリ祭」と呼んでいる。後年、大阪万国博覧会で来日したクレールは、東宝東和の川喜多長政(1903-1981)から「パリ祭」という言葉の由来を聞いて驚いたという。また、東京の下町出身の小説家・池波正太郎(1923-1990)は、少年時代にこの映画を見て、そこに描かれたパリの下町の人情に強い親近感を抱いたと随筆に記している。
1930年代の前半がクレールの時代とすれば、後半はフェーデやデュヴィヴィエの時代と言えるかも知れない。彼らの作品に見られるペシミズムやニヒリズムが日本の観衆の心をとらえた背景には、昭和4(1929)年の大恐慌以降の世界的不況、ファシズムの台頭や戦争に対する不安など、日本とフランスに共通する事情もあったとされる。
マリー・ベル(1900-1985)(『キネマ週報』233,1935.3【Z11-1848】)![]()
フェーデの《外人部隊》で、主人公の愛人と酒場の女の一人二役を演じた。この後、昭和13(1938)年日本公開のデュヴィヴィエの《舞踏会の手帖》で気品ある未亡人を演じ、日本のファンを魅了した。当時この他にも、可憐なアナベラ(1907-1996)、美男俳優のシャルル・ボワイエ(1899-1978)、戦前・戦後を通じ名優の名をほしいままにしたジャン・ギャバン(1904-1976)などが人気を集めた。
この時期の日本映画に対するフランスの影響は、同時代の映画人だけでなく、戦後に映画界で活躍することになる当時の映画青年たちにとっても測り知れないものがあった。映画を通じてのフランスに対する憧れと共感が一つのピークに達した時期と言える。
戦後のフランス映画
戦後、映画産業は再び隆盛の時代を迎えることになる。その中でフランス映画は、近作だけでなく、戦前日本で公開禁止になっていた名作も続々と公開され、アメリカ映画やイタリア映画などとともに洋画の人気を支えた。
戦前・戦中の作品としては、昭和23(1948)年にデュヴィヴィエの《旅路の果て》、翌年には、四大巨匠の中で《どん底》などを除いてあまり日本に紹介されていなかった、ジャン・ルノワールの《大いなる幻影》(ただし、この時公開されたのは戦時中軍部によって一部カットされたもの)、同27(1952)年には四大巨匠の次の世代にあたるマルセル・カルネ(1906-1996)の大作《天井桟敷の人々》などが公開された。
戦後の作品でも、詩人ジャン・コクトー(1889-1963)が監督した《美女と野獣》、ルネ・クレマン(1913-1996)の《海の牙》、《禁じられた遊び》、アンリ=ジョルジュ・クルーゾー(1907-1977)の《情婦マノン》、《恐怖の報酬》など多彩な作品が続々と公開され活況を呈した。
《天井桟敷の人々》(飯島正『今日のフランス映画』白水社,1952【778.25-I193k】)![]()
マルセル・カルネ監督による3時間以上に及ぶ詩的レアリスム映画の傑作。ナチス占領下という悪条件の中で制作されながら、フランス人の抵抗精神とフランス映画の底力を示し、日本においても高い評価と感動を呼んだ。その後、1979年にフランスでフランス映画史上ベストワン作品に輝いたのに続き、日本でも昭和55(1980)年12月下旬号の『キネマ旬報』で、日本公開外国映画史上ベストワンに選ばれている。
ヌーヴェル・ヴァーグ以後
1950年代後半になると、詩的レアリスムのような従来の映画の作風に反旗を翻す「ヌーヴェル・ヴァーグ」と呼ばれる映画運動が起き、その理論と実作においてなされた問題提起は、日本も含め世界中に反響をまきおこした。特に、ヌーヴェル・ヴァーグの代表的監督ジャン=リュック・ゴダール(1930- )の《勝手にしやがれ》などに見られる即興演出の手法は、当時の日本の映画関係者等にも大きな衝撃を与えた。なお日本でも、昭和35(1960)年から大島渚(1932-2013)、吉田喜重(1933- )、篠田正浩(1931- )ら若手監督による問題作が相次ぎ公開され、「松竹ヌーヴェル・ヴァーグ」と呼ばれた。本場フランスのそれと直接の影響関係はなかったが、1950年代から60年代にかけて世界各国で映画の革新を模索する動きがあり、日本の現象もその一環に位置づけられる。
戦後人気を集めたフランス映画のスターは、ジェラール・フィリップ(1922-1959)、ブリジット・バルドー(1934- )、アラン・ドロン(1935- )、カトリーヌ・ドヌーヴ(1943- )など数多いが、特にアラン・ドロンの人気は高く、昭和38(1963)年4月に第3回フランス映画祭に合わせて初来日した際も、ファンを熱狂させた。近年でも平成22(2010)年に「アラン・ドロン生誕75周年記念映画祭」が東京や京都で開催されるなどその人気の根強さを示している。
ヌーヴェル・ヴァーグ退潮後、フランス映画は停滞期を迎える。日本においてもアメリカ映画に押され、以前に比べてその存在感は希薄になり、かつてアラン・ドロン等を日本に招いたフランス映画祭もその後中断した。1980年代に入ってようやくジャン=ジャック・ベネックス(1946- )、リュック・ベッソン(1959- )、レオス・カラックス(1960- )ら若手監督の台頭もあり、また他の監督たちの話題作も続々公開されて、次第に活気を取り戻し現在に至っている。なお、フランス映画祭も平成5(1993)年に復活し、現在まで毎年開催されている。