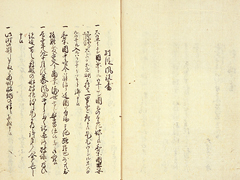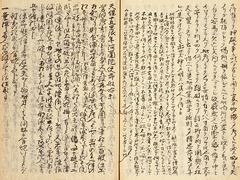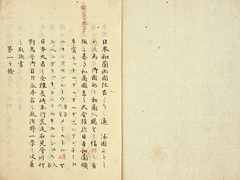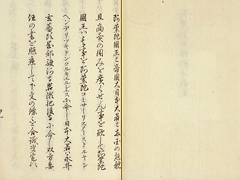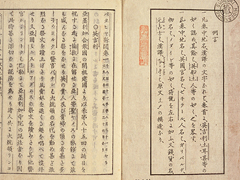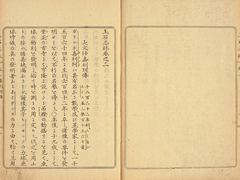第1部 歴史をたどる
4. 日本の開国と日蘭関係
(1)欧米の進出
1839年清国とイギリスとの間にアヘン戦争が勃発、我が国においても西欧諸国の侵略の危機が切迫して感じられようになる。この頃すでに定型化、簡略化していた「風説書」と別に、1840年以降アヘン戦争に関する詳しい情報が「別段風説書」として提出されるようになった。これは、アヘン戦争終結後も詳細な海外事情の報告として継続された。
長崎町年寄高島秋帆は、いち早く西洋砲術導入の必要性を唱え、幕府もしだいに関心を示すようになる。天保13年(1842)には、外国船は理由のいかんを問わずただちに打ち払うとした異国船打払令を緩和し、漂着した外国船には食料、薪水を給与して退去させることとした。幕府はオランダ商館を通じて、西洋諸国にも伝達することを依頼している(これは弘化4年(1847)に実行された)。
こうした形勢を見たオランダ国王ウィレム2世は、この機会に開国すべきことを幕府に勧告した。これにはシーボルトの助言もあったという。オランダの使節は天保15年(1844)長崎に入港し、国王の親書と献上品をもたらした。幕府はこの勧告を謝絶したが、日本近海に出現する欧米船は数を増す一方であった。
(2)開国
このような状況の中で、ペリー提督率いるアメリカ合衆国東インド艦隊が、日本を開国させるため派遣された。オランダはこれを機に日本との新条約締結を目指す。最後の商館長ドンケル・クルティウスはその使命を帯びて嘉永5年(1852)着任、アメリカ使節の来航を予告した。しかし、幕府は特段の策も講じず、嘉永6年(1853)浦賀に到着した米艦隊に1年の猶予を乞い退去させる。翌年(1854)再度来航したペリーの強硬な態度により、日米和親条約が締結され、我が国は下田、箱館を開くことになった。これに続いてイギリス、ロシアも日本との条約を結んだ。こうして、200年以上にわたる「鎖国」政策は終わりを告げた。
幕府は海軍力の強化の必要に迫られ、従来唯一の交流相手だったオランダに嘉永6年(1853)軍艦の購入を申し出る。翌年軍艦スーンビン号が長崎に到着、艦長ファビウス中佐のもと、3か月の短期間であったが、日本人に海軍伝習が行われた。同艦は安政2年(1855)幕府に寄贈され観光丸と改称、第2次海軍伝習の練習艦となった。この時にはペルス・ライケン中尉等22名の海軍軍人が教習にあたり、幕府発注のヤパン号(咸臨丸)で来日したカッテンディーケ大尉らにより引き継がれる。安政6年(1859)幕府の方針変更により長崎海軍伝習所は閉鎖されたが、これが日本人がオランダ人から組織的に直接学習するはじめであった。(2-5を参照)
日蘭和親条約は安政2年12月(1856.1)、長崎においてドンケル・クルティウスとの間に結ばれた。この時から出島への出入りが自由になったが、まだ貿易は従来の長崎会所統制のままである。
安政4年8月(1857.10)日蘭追加条約が締結される。これが日本が外国と結んだ最初の通商条約で、出島での貿易制限規定が緩和され、箱館でも貿易が許可された。ハリスが安政5年(1858)日米修好通商条約を結ぶとオランダも新通商条約の締結を急ぎ、その1か月後日米条約とほぼ同等の日蘭修交通商条約が結ばれた。オランダと日本の貿易は、商館のみが携わる会所貿易から個々の商人による自由貿易になり、貿易の有様には大きな変化が生じた。
オランダを代表する駐在機関も商館から領事館に移行した。初代の駐日総領事デ・ウィットは安政7年1月(1860.2)に着任した。総領事館はなお出島にあったが、長崎は独占的な貿易港としての地位をもはや失っていた。
(3)その後の日蘭関係
幕府は、公式に洋学の研究と洋書の翻訳をするため、安政3年(1856)「蕃書調所」を設立した。この機関が企画段階では「洋学所」と呼ばれていたことが示すように、開国後は英語、フランス語などの必要性が増し、学問の摂取もオランダ語のみを通じた「蘭学」から幅広い「洋学」に移行していった。蕃書調所には多くの洋学者が採用され、翻訳、研究は、従来の自然科学中心から政治、法律等の分野にも及んだ。蕃書調所は文久2年(1862)「洋書調所」と改称、さらに翌年(1863)「開成所」となり、維新後は東京大学の前身の一つとなった。(コラム 江戸幕府旧蔵の蘭書を参照)
開国にともない、オランダ商館長から提出されていた風説書は安政6年(1859)廃止された。しかし、欧米各国を中心とした海外事情を知る必要は依然としてあり、幕府は独自に海外情報を翻訳刊行する。これが『官板バタヒヤ新聞』である。
また、欧米の進んだ軍事技術を取り入れ、その進出に対抗することが急務とされた。英仏等の列強に比べて、オランダの国際的地位は以前のようではなかったが、軍事的知識の取り入れは、やはりオランダ語を介して行うのが便利であった。オランダ海軍軍人による海軍伝習が行われ、オランダ語の兵学教科書等も多く輸入、使用された。(2-5を参照)
文久2年(1862)幕府は海軍技術習得を主目的に留学生をオランダに派遣する。榎本武揚、西周、津田真道ら優秀な人材16名が派遣(うち職方1名は病のため長崎に留まった)され、造船学、航海術、医学、法学等を学んだ。西や津田は維新後哲学、法律等の導入の先駆者となる。(2-6を参照)
-
艦上で楽器を演奏するオランダ士官を描く長崎版画
「阿蘭陀人舩中之図」
(4)「蘭学」の終わり
開国によって、西洋の学問・技術は必ずしもオランダ語を通さず、英・仏・米・独等の諸言語から直接摂取する方向になったが、それでも従来の伝統からオランダ語を解する人が多く、蘭書を通じた摂取は引き続き行われ、医師のポンぺ、ボードイン、ハラタマらオランダ人の雇用もなされた。ポンぺは長崎に日本最初の西洋式病院を設立、ボードインもその後任として医学教育に尽力した。ハラタマは長崎で化学を教授、維新後は大阪舎密局(理化学の専門学校)の教頭となった。また、シーボルトも再来日し、幕府に献策を行った。
維新後もオランダの優れた水利土木技術等は重視され、ファン・ドールン、デ・レーケ、エッセルらの技師が「お雇い外国人」として貢献している。また、幕府の機関や蘭学塾で洋学を学んだ人々は、明治政府に仕え、あるいは在野の教育者、著述家となって新しい学問技術の発展に貢献することになる。
こうして、開国から明治維新にかけての時期に、洋学にとってかわられ「蘭学」の時代は終わりを迎えた。しかし、オランダは西洋諸国のうち江戸時代唯一の交流相手であり、オランダ語、オランダ人を通じて西洋の学術、知識を学び、海外情報を得ていたことは、日本の近代化、西欧化を準備するための基礎をつくることになった。
Copyright © 2009 National Diet Library. Japan. All Rights Reserved