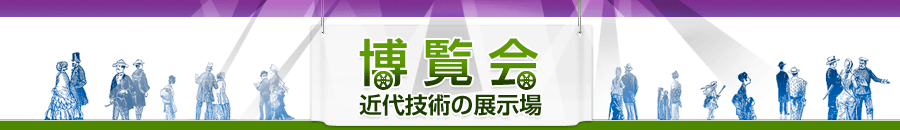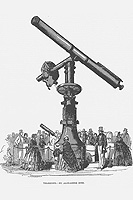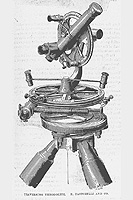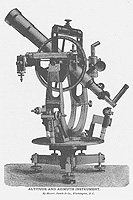望遠鏡・顕微鏡
望遠鏡
 画像は、1900年第5回パリ万博の光の宮殿(Palais de l'Optique)というパビリオンに展示された、史上最大の屈折望遠鏡。焦点距離は55m、レンズの直径 125cm。望遠鏡の位置は固定され、フーコー(J. B. L. Foucault)のシデロスタットという鏡を使った装置で、どんな方向からの光も望遠鏡に導くようになっている。入場者は実際に天体を観覧できたため、入場者の列が夕方から夜半まで続いた。
画像は、1900年第5回パリ万博の光の宮殿(Palais de l'Optique)というパビリオンに展示された、史上最大の屈折望遠鏡。焦点距離は55m、レンズの直径 125cm。望遠鏡の位置は固定され、フーコー(J. B. L. Foucault)のシデロスタットという鏡を使った装置で、どんな方向からの光も望遠鏡に導くようになっている。入場者は実際に天体を観覧できたため、入場者の列が夕方から夜半まで続いた。
1608年にオランダの眼鏡師リッペレイ(H. Lipperhey)が、水晶でできた凸レンズの対物レンズと、凹レンズの接眼レンズを組み合わせた屈折式の遠距離観察器具を作ったのが最初の望遠鏡といわれている。翌年夏には、ガリレイ(G. Galilei)がリッペレイの発明を噂に聞き自作に成功し、様々な発見をしたため、この凸レンズと凹レンズを組み合わせた方式をガリレオ式とよぶ。
その後、1611年にケプラー(J. Kepler)が凸レンズを二つ使った望遠鏡を発明、ガリレオ式と違って倒立した像が見えるが、倍率をあげても視界が狭くならない利点があった。1655年には、オランダのホイヘンス(Huygens)兄弟がレンズの新研磨法を開発、長さ3.3mの望遠鏡で土星の環の形状を確認し、衛星チタンを発見した。
屈折望遠鏡は、像の縁が色づいて像がぶれてしまう、色収差という光学的欠点があった。1668年、イギリスのニュートン(I. Newton)は初めて対物レンズの代わりに凹面鏡を用いた反射望遠鏡を製作し、この欠点を見事解決した。
当時の屈折望遠鏡は、作れるレンズの直径として10cmが限度だったため、さらに倍率を上げたい場合は大口径の反射望遠鏡を作るしかない。1851年に、蒸気ハンマーの発明で有名なナスミス(J. Nasmyth)が製作したいわゆるナスミス式反射望遠鏡はその一例である。
しかし、屈折率の異なるレンズを組み合わせて色収差を無くした色消しレンズの発明、無色透明な光学ガラスの開発が進み、屈折望遠鏡も巨大化が進んだ。1855年の第1回パリ万博には、イギリスのチャンス・ブラザーズ社が口径74cmの光学ガラス材料を出展している。1893年のシカゴ万博に出品された、クラーク(A. G. Clark)が製作した口径101.6cmの屈折望遠鏡は、ヤーキス天文台に設置され、現在でも実際に使用されている赤道儀式(日周運動にあわせて星を追尾できる架台)の屈折望遠鏡では最大である。冒頭画像の口径125cmの屈折望遠鏡は史上最大であった(のちに解体)。
しかし、屈折望遠鏡は大型になるほど筒が長くなってしまうため、20世紀には大型望遠鏡は反射望遠鏡が主流になっていく。
顕微鏡
1590年頃、オランダの眼鏡職人ヤンセン父子(Z. Jansen, H. Jansen)が、筒の両端にレンズをつけ、その2枚の凸レンズを利用して小さなものを見たのが、顕微鏡の始まりだと言われている。しかしその性能は粗末なものであり、科学的拡大器具とは言い難かった。
1665年、フック(R. Hook)は対物レンズと接眼レンズを組み合わせた複式顕微鏡を製作し、Micrographiaを発表した。その中で複式顕微鏡の製作法を図説し、使用法を記述したのだが、同時に生物の細胞の発見という生物学上の大発見をした。ちなみに、1683年にはA.レーウェンフック(A. V. Leeuwenhoeck)が球レンズによる高倍率の単式顕微鏡を発明し、バクテリアの発見にもつながったが、彼以外には使いこなしにくいものだった。
しかし、接眼と対物の二つのレンズを用いた複式顕微鏡には、望遠鏡と同様に色収差という光学的欠点があった。この問題は長い間解決しなかったが、色消しレンズが発明され、さらに球面収差の解決法も見つかって、1829年、イギリス人リスター(J. J. Lister)によって色消し顕微鏡が発明されたことによりようやく解決した。
上記画像は、こうした改良が施された複式顕微鏡で、1851年ロンドン万博には複数の出品者が出展している。1876年のフィラデルフィア万国博覧会ではコンタクトレンズ製品で現在も有名なボシュロム(Bausch & Lomb)社 (創業時は眼鏡屋)が顕微鏡を出品し、いくつかの賞を受賞した。
- 参考文献:
『世界の顕微鏡の歴史』 小林義雄 1980 <MC111-23>
田中新一 『顕微鏡の歴史』 九州文庫出版社 1979 <MC111-12>
吉田正太郎 『望遠鏡発達史』 上下巻 誠文堂新光社 1994 <MB51-E27>
吉田正太郎 『巨大望遠鏡への道』 裳華房 1995 <MB51-G3>