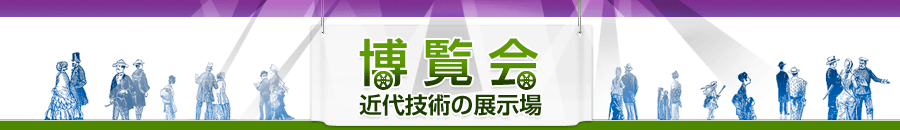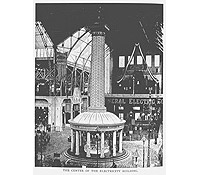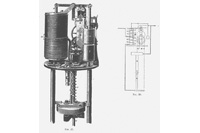電灯
産業革命後、工場の稼働率を上げるために労働者が夜間も働けるような照明への期待が高まり、1800年頃からは石炭ガスの燃焼を利用したガス灯が使用されるようになった。石炭ガスは初期の内燃機関であるガスエンジンの燃料として技術革新をもたらしたものの、ガス灯は作業用照明としては明るさが不足していた。
電灯の歴史は、気体中の放電を利用したアーク灯に始まる。1815年、イギリスの化学者デーヴィ(H. Davy)が、王立研究所においてヴォルタ電池2,000個を電源としてアーク灯の実験を行って強烈な光を出すことに成功した。が、長時間電力を供給する電源の開発や電極間隔の改善などの課題があり、なかなか実用化には至らず、これらを解決してアーク灯が最初に使用されたのは、1862年イギリスのダンジネス灯台においてであった。アーク灯は光が大変強烈で紫外線を多く含んでいたため、屋内照明には不向きであった。
その問題を解決する存在として注目されたのが白熱電球である。白熱電球はガラス内のフィラメント(繊維)に大量の電気を流すと白熱して発光する原理を利用しており、実用化のためにはガラス球体内の真空化の実現、高温でも切れにくいフィラメント材料が必要だった。
1878年、イギリスのスワン(J. W. Swan)は、シュプレンゲル(H. J. P. Sprengel)の発明した水銀真空ポンプを用い、炭化させた木綿糸をフィラメントとした電球を開発した。1879年には、アメリカの発明王エディソン(T. A. Edison)も炭素フィラメントを用い、寿命約40時間の電球を作ることに成功した。エディソンはフィラメント材の研究をさらに続け、日本の竹を炭化したフィラメントを作り、パリ国際電気博覧会(1882年)で話題となった。炭素フィラメント電球の特許はエディソンが先に出願して権利を取得したため、スワンは発明権をめぐって争ったが、後に事業提携して和解している。
白熱電球は、1893年のシカゴ万博や1900年第5回パリ万博の頃になると、会場内の各所で使用され、単なる照明としてだけでなく、イルミネーションとしても人々を楽しませた。
その後もフィラメント材の研究は世界各地で続き、素材として溶融温度の高いタングステン鉱石の粉末が注目を浴びる。20世紀に入るとガス入りタングステン電球が発明され、現在でも使用されているタングステン電球の開発へとつながっていった。
一方で、アーク灯に連なる放電灯の研究も進み、1902年に米国のクーパー=ヒューイット(P. Cooper-Hewitt)は水銀灯を発明。ネオン灯(ガス放電の一種)や蛍光灯(水銀灯の青緑がかった色や紫外線を改善したもの)の発明へとつながっていった。
- 参考文献:
岩本洋 『絵でみる電気の歴史 : 図版300枚で物語る電気の発見の旅』 オーム社 2003 <ND21-H5>
高橋雄造 『百万人の電気技術史』 工業調査会 2006 <ND21-H140>
直川一也 『電気の歴史』 第2版 東京電機大学 1994 <ND21-E48>