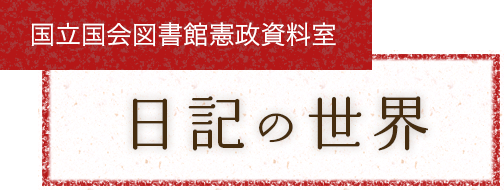キーワード一覧
日記から引用した一節を、特定の内容でまとめてご覧になれます。
キーワード:海外
文久2年8月2日(1862年8月26日)
穏やかな海へ出航
海外 詳しく
快晴。風少く海面油を流せし如く、夕七ツ時御船当港出船、志州浦え向。夜中遠州灘え進む。この灘は兎角[とにかく]波立荒き所なれ共、風これ無きに付致て穏静。
文久2年12月21日(1863年2月9日)
オランダ船の上で釣ったものは
海外 詳しく
過午四時過頃Dolfijn[イルカ]一尾を釣る。…本邦豆相州辺にて「シイラ」と唱ふ者と全く同物の由、我水夫共等いゝあへり。
文久3年2月9日(1863年3月27日)
ナポレオンを偲んで
海外 詳しく
烈翁[ナポレオン]謫居[たっきょ]の時、この所に住し今を去る○終無き人の数に入たる所なり。
文久3年4月16日(1863年6月2日)
オランダ到着
海外 詳しく
六時半スチュールボールドの方に当て、和蘭[オランダ]セーランドの内スコーウェンの地方を見る。■して水面を抜く事高からず。
文久4年1月3日(1864年2月10日)
日本を離れる前、鹿児島沖にて
海外 詳しく
波穏に船平にして、始て蒸気の力を専にするを得たり。漸く薩の地方に近寄て航す。海門嶽[開聞岳]遙に波光潮煙の外に聳[そびえ]て、宛然月夜の芙蓉に似たり。眺望いと面白し。夜に入り風雨一並来り、天色昏黒枕上点滴に霑ふも苦し。
文久4年2月21日(1864年3月28日)
壮観、ピラミッド、スフィンクス像!
海外 詳しく
それより一巨寺に遊ぶ。市外阜上にあり、凍石を彫刻して柱梁とす。高さ凡十余丈もあるべく、上は金碧五彩熀燿目を眩し、下は凍石を舗き列[つら]ね、回廊水盤華■にして観るべし。是礼拝堂にて門口砲卒警衛せり。寺外より望めは市府一目了然にて、有名の巨塚人首の壮観も遥[はるか]に見えり。
明治3年9月17日(1870年10月11日)
渡仏の洋上での想い
海外 詳しく
揚碇後、殆んど二十日になれども一島又は一舟を見ず。時に因て鷗[かもめ]の如きなる鳥の飛ぶあり。往昔「コロンヒス」(西班牙人[スペイン人]初て米利堅[アメリカ]を発見せし人)が米利堅を発見せしも、かくやあらんと思ひしられたり。
明治5年9月18日(1872年10月20日)
あるロシア人の訪問
海外 詳しく
夕景一人の魯西亜人[ロシア人]来る。よく日本を解す。その内に同行せん事を乞ふ。因て同車にて行き、夜八字[八時]帰る。この人は仏[フランス]にて我語を学びたりとて、よく字を読む。我も大に弁を得たり。故に一字づゝ互に教ゆる事を約す。
明治6(1873)年3月10日
ドイツで動物園、水族館を見物
海外 詳しく
午飯後、禽獣園に遊び、夜鳥魚館に往く。
明治6(1873)年8月27日
ウィーンで目にとまったものは
海外 詳しく
この〔ウィーン〕府の目に留まるものは、美婦にして至処美人あらざるはなし。しかして多くは上郎と云ふ。実にこの府の繁花を知るべし。
明治11(1878)年7月29日
憎い南京虫の攻撃
海外 詳しく
燭をもって枕を検ずるに、果して「ワンドロイス」歩き居るを見て急ぎこれを殺し、しかる后寝に就く。時に既に三時頃たり。やや久しくして夢甚煩悩なり。醒て見れば両瞼ホゝと腮[あご]のところを更に三、四ヶ所刺され居たり。予怒に堪へ兼ぬれども「ワンドロイス」のあるを見ず。
明治11(1878)年8月23日
シベリアで写真を集める
海外 詳しく
十時半、予は当府の写真を買ふため、寺見生と同車して先発す。日耳曼人[ゲルマン人]の写真師某の家にて二枚を買入たり。
明治11(1878)年9月2日
国境の街、買売城の訪問
海外 詳しく
午後一時「コミサル」と同車にて、支那領売買城[マイマツチン]に入り、支那の首長を訪ふ。支那と「キャクタ」町家の境は、僅[わずか]に五十尺(サーゼン)の中立地あるのみ。故に恰[あたか]も一府の如し。
明治11(1878)年9月18日
鎮台の歓迎セレモニー
海外 詳しく
さて鎮台の邸に至れば、鎮台は庁前の戸外に出て予を迎へ陸軍楽隊は庁前に並立つ。予が鎮台と共に戸に入りしとき楽起れり。客間に入れば、当府の文武官并二十四五人ばかり一切に駢立[べんりつ]せり。鎮台は一々予に引合せり。
明治11(1878)年9月20日
鱗(ウロコ)談義
海外 詳しく
予かねてこの魚の必ず北海道石狩「テシホ[天塩]」等河にも在るべきを思ひ居たるにより、その形を熟視し、かつ背筋通り三条の鱗を数へしに、一条ごとに三十五個ありたり。
明治18(1885)年3月16日
詳しく
午後六時半、李相道台[どうだい]及び通弁を携帯し来る。食後使事を談ぜんと欲し、別室に誘引し余先づ彼に告曰く、聞く所に拠れば、閣下全権委任を受たりと、果し[て]しかれば、余実に欣躍に堪へず、しかるに全権大使の任、必ず先づその国都に入り皇帝に謁を請ひ、携帯する所の国書を捧呈せざるを得ざるの職務あるをもって、節をこの地に駐ずるを得ざるをもってす。李曰、我皇帝尚幼沖[ようちゅう]にあるをもって外国の使臣に接せずと。余又曰、皇帝幼沖にして引接に便ならざる、皇太后垂簾[すいれん]政務を執る、帝に代て謁を賜ふも可なり。李曰、我国風婦女子外人に接せず、閣下能[よ]くこれを知るべしと。
明治20(1887)年10月8日
汽車の中の反省会
海外 詳しく
〇九時停車場より発車す。〇車中三人の懺悔[ざんげ]話あり。奇極る。例により森最も多罪、石黒これに次ぎ、谷口割合に少なり。
明治21(1888)年1月13日
石黒のドイツでの観劇
海外 詳しく
〇午後六時半谷口森江口を招き、山口と共に独乙[ドイツ]テアートルに赴き、十一時帰宅す。Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Schauspiel in 5 Aufzügen von Goethe. Pittschau男, Geszner女, Pospischil女.
明治21(1888)年1月14日
樺山資紀、ルーブル宮殿に行く
海外 詳しく
晴。午後ルーブル宮殿を縦覧す。
明治21(1888)年7月5日
森林太郎、愛の別れ
海外 詳しく
〇車中、森はその情人の事を語り、為に愴然たり。後互に語なくして仮眠に入る。
明治21(1888)年7月27日
森林太郎、愛の行方
海外 詳しく
〇今夕多木子報曰、その情人ブレメンより独乙[ドイツ]船にて本邦に赴きたりとの報ありたりと。
明治24(1891)年11月10日
シンガポールのホテル事情
海外 詳しく
午後第四半、新嘉坡[シンガポール]着す。ルフールホテルに一泊、取扱甚だ不可なり。食物もまた甚だ不味[まずい]。始めて仏船の美味を感ぜり。
明治24(1891)年11月30日
アレキサンドリアの様子
海外 詳しく
日曜午前五時、アレキサントル着す。天気にして恰[あたかも]春陽の如し。高楼層閣櫛比し、旧時の大都府に負かざるべし。
明治26(1893)年8月18日
カナダの大富豪を訪問
海外 詳しく
午後当府において、百万の財産家(Million earl ミリオン イエール)と称するDunsmuir ダンスミュイア氏殿下を訪問し、自宅に来臨を請ふ。依て殿下に陪し、同人の邸宅に至る。海浜丘陵上に建築せるをもって、ジラルジヤ海峡を俯瞰[ふかん]し、兼てまたヴィクトリヤ全市を一眸の下[もと]に集め、風景最も宜し。暫時庭園を逍遥し、客室に入り家族と対話の末、同人に送られホテルに還る。
明治27(1894)年4月17日
バチカン見物
海外 詳しく
「サン・ポーロ」寺は、「タイバー」河畔にあり。彼の耶蘇[ヤソ]の高弟「セント・ポール」の墳墓の地に、「サン・ピエトロ」寺に均しき伽藍[がらん]を建築せんとて、法王の勧誘に依り「コンスタンチン」大帝の起工したる所なり。後歴代の帝王法王等は、切[しき]りに荘厳なる修飾を施し、羅馬[ローマ]寺院中最美最麗最大なるものとなりたり。
明治27(1894)年8月19日
ニューヨークで寺島と談話
海外 詳しく
本日、寺島伯来訪。胸襟を披ひて、本邦及海外に関し種々談話を為し、殊[こと]に快楽を覚へたり。
明治27(1894)年8月21日
観劇を通じてアメリカ人の日本観に触れる
海外 詳しく
来訪者殿下と談話中、余は殿下より暫時の御暇を請ひ、姪剛十郎の案内に依り「ミカド」と称する劇場に赴き、米人[アメリカ人]が如何なる思想と考按とをもって我帝国の状態を模写するやを一覧し、了[おわっ]て屋上園(ルーフ・ガーデン)を観覧して、直に帰館せり。
明治40(1907)年8月19日
旧知の宣教医を訪ねる
海外 詳しく
英国宣教医グレーを訪ふ。午睡中にて面会せず。氏は、十五年前余が単騎遠征の途次、この地に来りし時の旧相識なり。彼は団匪[だんぴ]の変、家を焼かれ、家財を奪はれ、身をもって浦港[ウラジオストク]に逃れしも、事収ればまた旧の如し。その忍耐感ずべし。
大正5(1916)年5月21日
車窓から見たスウェーデン
海外 詳しく
汽車中、山間森林を通過す。景色よし。人気質朴一般に露国[ロシア]より富有に見ゆ。
昭和7(1932)年8月30日
衆議院書記官長のドイツ国会見学
海外 詳しく
Nazisは全員BraunのUniformに革のBandで入場着席。とても壮観偉観だ。しかも三分の一以上を占める優勢ぶり。
昭和11(1936)年8月1日
ヒトラーが登場するベルリンオリンピック
海外 詳しく
四時少し過ぎ、大総統(Führer)Hitler氏幕僚を随[したが]へ入場。花わ一斉に手を揚げHeil-Hitlerを叫ぶ。各国々旗掲揚。Olympiaglockeを鳴らす。かくして各国選手の入場式始まる。…日本は二十五六番目(中央)に大島旗手を先頭に堂々と入場。
昭和16(1941)年3月12日
ローマにて花輪を捧ぐ
海外 詳しく
11a.m. Matteucci中将、Talarigo中佐の案内でPantheon、無名戦士の墓及Fascist殉難者の墓に花輪を捧ぐ。
昭和20(1945)年12月13日
サンタ・ルチア祭
海外 詳しく
何だか少女の歌が聞える。夢かと思って目がさめると、Santa Luciaの少女がローソクを頭にし白衣でCaféとCakeを持って来た。Luciaの歌が終った。何この少女がと、更に眼を見はると何んだLillanであった。CaféとCakeを床の上で食べる、成る程これがLucia祭か。